今回はロアルド・ダールの児童小説『夢のチョコレート工場』とカルト的な人気を誇る1971年『ウィリーウォンカとチョコレート』と大ヒットした2005年『チャーリーとチョコレート工場』の謎に迫りたいと思います!
2005年『チャーリーとチョコレート工場』についてはこちらで更に解説してますので是非!
どうやって夢のチョコレート工場が出来たのか!ウォンカのモデルは実在した!?
大人も子供も惹きつけてやまない『夢のチョコレート工場』はどうやって誕生したのでしょうか。それは原作者ロアルド・ダールの幼少期の出来事が深く影響していたのです!
ロアルド・ダールの幼少期の思い出を綴った自伝的エピソード集『Boy』にそのヒントはありました。この本は1920年から30年代までの暮らしと、寄宿学校での思い出などと共にお菓子とチョコレートについてのエピソードが登場します。
その中でもロアルドダール自身がチョコレート工場の物語を作る際に影響を受けたという、レプトンスクールでの思い出を見ていきましょう。
ロアルド・ダールが寄宿していたレプトンスクールでは上下関係がとても厳しくいじめや理不尽な体罰などがあった事が生々しく書かれています。そんな、抑圧的な環境なレプトンスクールでしたが、普段は理不尽ないじめをしてくる上級生や辛い境遇の下級生たちを喜ばせる出来事がありました。
レプトンスクールでは時々、キャドバリー社が新商品のチョコレートをテストするため、生徒たちにサンプルのチョコレートを箱で配っていたのです。全生徒に配られた箱の中には何枚かの試作品のチョコレートと点数と感想を書き込む紙が同封されていて、生徒たちは喜んで試作品のアンケートに答えていました。この時ばかりは全員が幸せな気持ちになっていたのです。
生徒の中でもとりわけロアルド・ダールは試作品のアンケートに真剣に取り組んでいました。
そしていつしか、厳しい寄宿学校にいる子供達を幸せにできるチョコレートを作ったキャドバリー氏に認められるようなチョコレートを作りたいと思うようになったのです。
自伝『Boy』でチョコレートのエピソードの最後はこのように締めくくられています。
それは楽しい夢だった。それから35年たって、2冊目の子供向けの本のプロットを考えている時、あの小さなボール紙の箱と、なかに入っていた新製品のチョコレートのことを思い出して、『チョコレート工場の秘密』という本を書き始めたことは疑う余地がない。
Boy: Tales of Childhood 著 ロアルド・ダール 日本語訳 永井 淳
こうしたロアルドダールの経験から夢のチョコレート工場は誕生したのでした。しかしもう一つ気になる事があります。それはウィリー・ウォンカにはモデルがいたのか?という疑問です。
調べてみましたが、物語の誕生した経緯については語られていますが、ウォンカについてはどこを探しても書いていませんので、真相は分かりませんでした。
ですが!
あくまでも個人的な推測ですが、キャドバリー社のキャドバリー氏と幼い頃のロアルド・ダールの理想とする自分を混ぜたのではないかと思っています。
お菓子を通じて、どんな子供でもつかの間の幸せを提供するギャドバリー氏。理想とするお菓子をとことん追求するロアルド・ダールが思い描いていた過去の自分。この二人を混ぜたらウィリー・ウォンカに近いと思いませんか?
お菓子メーカーのバトルは本当の話だった!?
作中の中でウォンカが工場を閉鎖したのは、競合相手による産業スパイが原因でした。このエピソードが語られた時、ファンタジーの世界でもどこか現実的な話だと思いませんでしたか?
そう思われた方は感が鋭いです!
なぜなら、産業スパイのエピソードは本当にあった出来事だったのです!
ロアルドダールの故郷イングランドでは2大チョコレートメーカーが存在していました。それは、キャドバリー(Cadbury)とローンツリー(Rowntree’s)の2社です。1920年頃の話ですがこの2社はライバル関係にあり、競合相手の工場に従業員として産業スパイを忍び込ませ企業秘密を盗もうとした事がありました。
何十年後にチョコレート工場の物語を執筆する際にロアルドダールが、はこの事件を参考にしたのは間違いないでしょう。
原作とデップ版チョコレート工場では単に閉鎖した理由として語られるのみですが、独自色の強い1971年版チョコレート工場では『産業スパイ』というキーワードがラストシーンに繋がる伏線として使われています。
この1971年版ではスラグワースというウォンカのレシピを盗もうとするオリジナルの人物が登場します。
スラグワースはウォンカが開発した貧しい子供のための永遠に消えないキャンディー『ゴブストッパー』のサンプルを渡してくれれば莫大な報酬と変えると、ゴールデンチケットを持つ5人に囁く謎の人物でした。
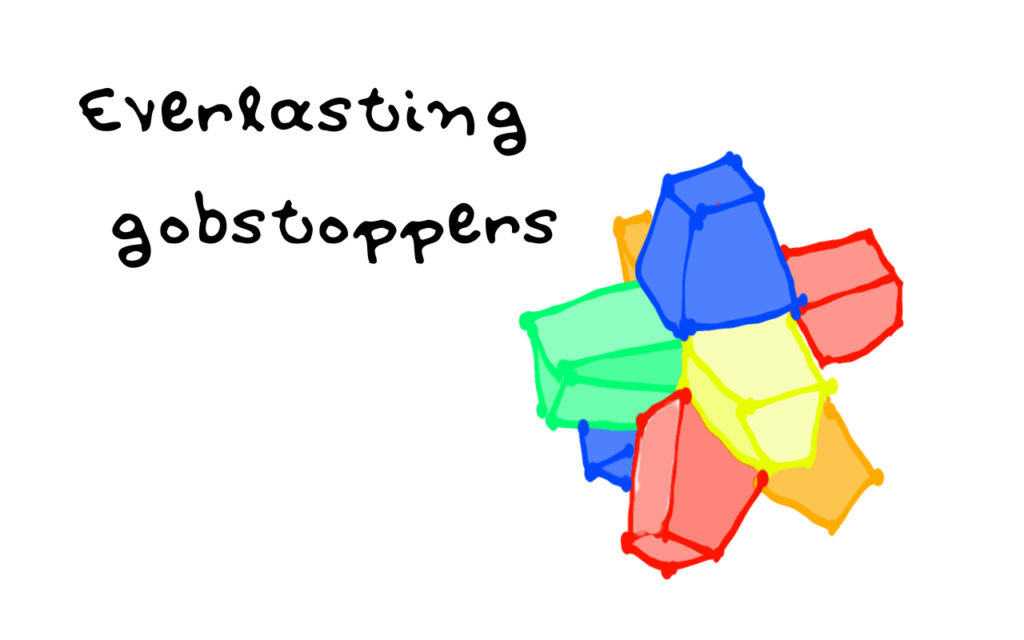
ゴブストッパーとはイギリスの実在するお菓子です。Jawbreaker (ジョーブレイカー)』とも呼ばれています。
原作者のロアルド・ダールの自伝によると、小さい時に食べていたとの事。
しかしロアルドダールはキャンディーより、タイヤ味でお馴染みのリコリスが好きだったらしいですよ!
1971版のオリジナルエピソードもチョコレート工場の世界に違和感はありませんでした。ですが、ウォンカは産業スパイによって従業員を全員解雇したはずじゃなかったのか!という矛盾は無視できません。
産業スパイというエピーソードを膨らませ新たな展開をした1971版ですが、2005年では無かった事になっていました。
それは、物語の展開優先で、ウォンカの人間不信という重要な設定を無視した事がリメイク版では無くなった理由でしょう。
ウォンカはなぜ工場見学を計画したのか
原作と映画のラストで工場見学の目的は、工場の後継者探しの為のテストだったと明かされます。しかし、ウォンカにはもう一つの目的があったように思います。
それは自分の世界に閉じこもっていた自分を変える事です!
原作で、チャーリーだけが残ってガラスのエレベーターに乗るウォンカは『上と外』と書いてあるボタンを押した後、こんな言葉を言うのです。
長年、このボタンを押したくてむずむずしていたんです! しかし、いまのいままで押したことはなかった! 何度も何度もそそられた! そう、まさしく、そそられた! しかし工場の屋根にとてつもない大穴をあけると思うと、たえられなかった! さあ行くぞ、よし! 上へ外へ!」
チョコレート工場の秘密 著ロアルド・ダール 日本語訳 柳瀬尚紀
きっと、ウォンカ自身もこのままではいけないと思っていたのです。
誰とも繋がろうともせず家族も子供もいない自分が倒れた時、誰が工場を経営していくのか。しかし、他者を受け入れて後継者にすると、以前のように工場の秘密が漏れてしまうかもしれない。ウォンカはこのジレンマを抱えていたのでしょう。
そのジレンマは自分の求める真の後継者が見つかった時に解決してくれると信じていたのです。
そんなウォンカの前に現れたチャーリーという存在は、どれほど待ち侘びていたのか計り知れません。
そして、ガラスのエレベーターはロケットのようにとてつもないスピードで屋根を突き抜け外へと出たのです。
ウォンカにとってはチョコレート工場は自分と同じ。そんな大切な工場の屋根を壊してまで外に出るという事は、自分の殻を破ったという暗喩として考える事ができるのです。
『上と外』というボタンには、自分を変えてもっと上を目指すんだ!自分のお菓子をもっと広げるんだ!という決意を込めたのではないでしょうか。
3人のウィリーウォンカの違い
原作のウォンカは底抜けに明るく、陽気な紳士のイメージで描かれています。
ジーンワイルダー版は飄々として陽気なんだけど悲しみを背負った紳士。
ジーン・ワイルダーがウォンカの役を引き受ける際、監督にひとつのシーンを撮る事を要求したのです。そのシーンこそ、閉鎖された工場の門が開き、ウォンカが登場するシーンです。
私が彼らに初めて会う時、杖を持ってドアから出て、足を引きずって人混みに向かって歩きたい。群衆はウィリー・ウォンカが体が不自由であるのを見た後、彼ら全員が自分自身にささやき、そして死ぬほど静かになるだろう。 私が彼らに向かって歩くと、杖は私が歩いている石畳に突き刺さるが、私はそれでも気づかずに歩き続ける。やがて私は前に倒れ始め、地面に着く直前に美しい前宙返りをして跳ね返り、大きな拍手を受けるだろう。
https://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Wonka_%26_the_Chocolate_Factory
なぜこのシーンを撮りたいのか監督に聞かれたジーンワイルダーはこう答えています。
その時から、私が嘘をついているのか真実を語っているのか、誰もわからなくなるだろう
こうした、ジーン・ワイルダーのこだわりから唯一無二のウィリー・ウォンカが誕生したのです!
そして、2005年のジョニー・デップ版は子供がそのまま大人になったようなキャラで、言ってしまえばアダルトチルドレンそのものです。
ティムバートンが大きくウォンカのイメージチェンジしたのはちゃんと意味があるのです。
原作ではウォンカについては詳しく描かれておらず、彼がどんな人生を送って今に至るかは読者の想像に委ねる形でした。
その説明されていない部分をティムバートンは想像を膨らませ歪な親子関係というバックボーンを付け足したのです。完成したストーリーに後から足すのは蛇足になりがちですが、むしろウィリー・ウォンカの魅力が増したように思います。
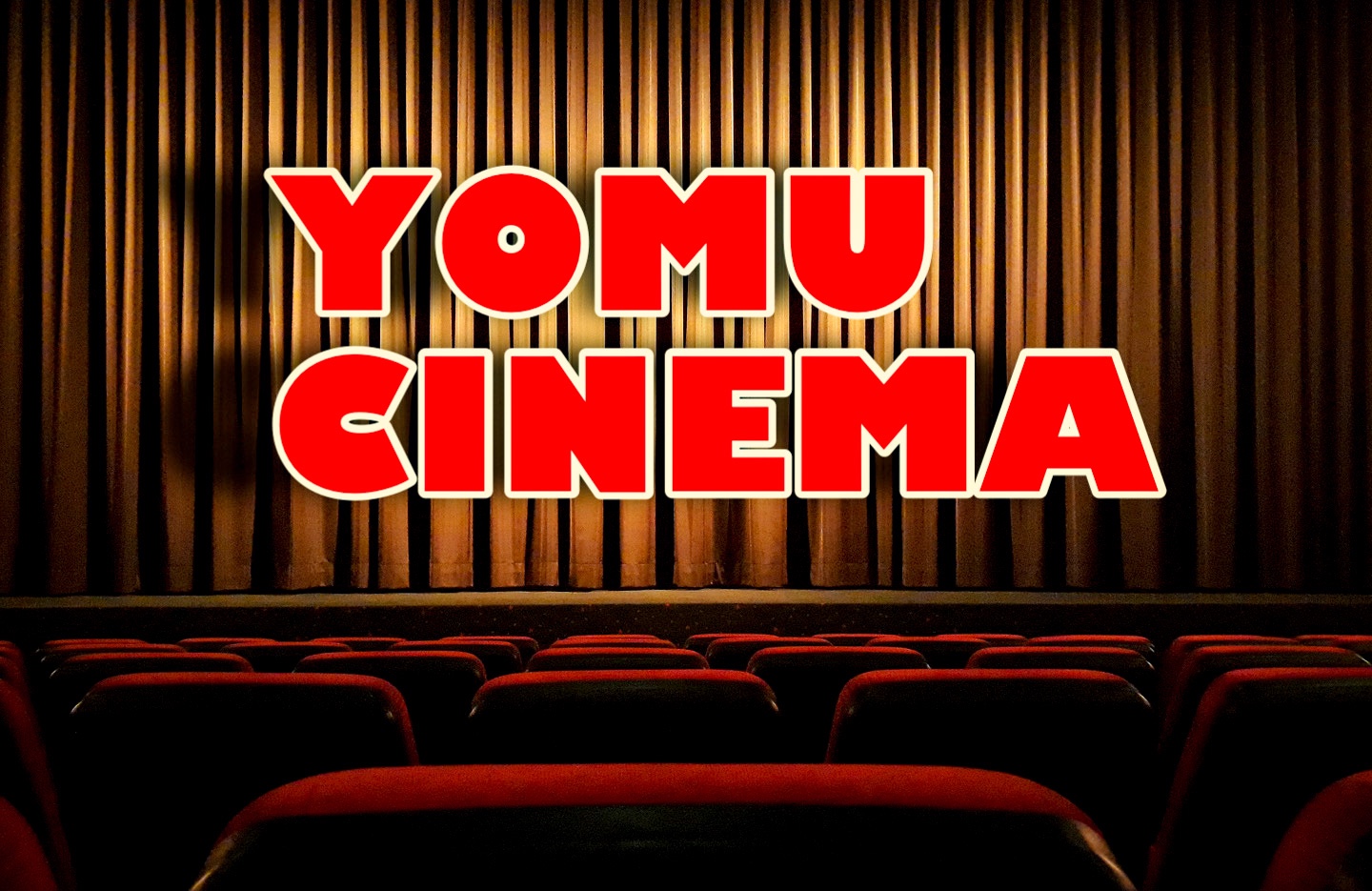


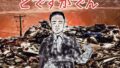

コメント